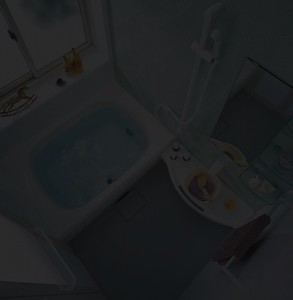耳鳴り。
耳鳴りがするとその方向に霊がいるだとか、ラップ音は霊が現れる前兆だとかいう話がある。
しかし耳鳴りなんてそのメカニズムは解明されてるし、ラップ音も昼と夜との温度差で建物が僅かに膨張収縮し、軋むだけだと言われている。
実は小さい頃、俺はよく耳鳴りやラップ音を聞いた。しかしその場にいる人に話しても大抵の場合、皆聞こえなかったという。
耳鳴りはまだしも、ラップ音に関してはおかしくないだろうか?
建物が軋んだのなら、そこにいる全員に聞こえるはずではないか。
そんなことが何度かあると、周囲は気味が悪いといった反応をする。人は得体のしれないものには拒否反応を起こすもので、あまり変なことを言うんじゃないと親に強く叱られてからはそれを口にすることはなくなった。
そしていつしか、耳鳴りやラップ音を頻繁に聞くこともなくなった。
その雪山に行くまでは。
当時大学一年生の俺は、雪山のとあるペンションに住み込みで働いていた。
ペンション内の一切の雑用は、一年生の俺たちの仕事だ。
朝6時、起床。
すぐに客に出す食事の準備にかかり、それが終わると朝食を摂る。
次は大浴場(客室にもユニットバスはあった)とトイレやロビーの掃除。
その後昼食を食べ終えると、少し外で滑ってから客室の清掃を済ませ、夕飯の準備。
客が食べ終わり片付けが終わると、自分たちも夕飯を食べてナイターでスキー。ペンションに戻った頃にはくたくたで、風呂に入ったらすぐ寝る。
というのが日課だった。
毎日同じことの繰り返しで娯楽もない。ちなみに住み込みで食事付きだから、給料も出ない。
何度か脱走してやろうと思ったが、週に一度だけ開かれる飲み会と、他大学から同じように住み込みで働く一年生の女の子と仲良くなったことが、この自堕落な俺を支えていた。
それが無ければ正直監獄にでもいるような気分だっただろう。
そしてそこから雪山のラブロマンスが生まれる。という美しいストーリーは残念ながら無いのだが、当時俺が体験したことを黙って聞いて欲しい。
何故だか、今話さなくてはいけない気がする。
ペンションで暮らし始めて一週間。
俺は早くも異変を感じていた。
そのペンションは一階がロビー、食堂、大浴場と従業員の寝室。二階が8部屋の客室という小さな造りだった。
地下倉庫が二つあるのだが、何故かその一つに行くと毎回耳鳴りする。また、二階の客室を掃除しているときラップ音を聴くことが度々ある。嫌な感じだ。
いや、きっと高山で気圧が違うので、こういったことも起こるのだろう。
先輩に諌められていたこともあり、何より同じ場所で働くE子を怖がらせたくなかったので、俺は誰にもそれを話せずにいた。
そんなある日。
こもり始めて一ヶ月くらいだったと思う。
俺は客室の掃除をしていた。
典型的な洋室で、ドアを開けてすぐ左手にユニットバス。奥にベッドが二つ並んでいる。いつものように、ユニットバスの掃除をした後でベッドルームに取り掛かる。
同じフロアではE子が掃除をしている。
俺が四部屋。E子も四部屋。
どっちが先に終わるか競争だ。
ベッドメイクまで終わり、最後にもう一度掃除機をかける。
そのとき、耳鳴りとラップ音がほぼ同時に聴こえた。
だが、一ヶ月も同じようなことが起こるといちいち反応していられない。
特に気にせず、俺はそのままベッド周りを入念に掃除していた。何しろ、髪の毛一本落ちてるのが見つかっただけで女将にたっぷりといびられるのだ。
その一本を見つける手間があれば、テレビを観てないで掃除を手伝ってほしいものだ。
そんな文句を言いながら床を掃除する俺の視界の隅に、部屋に入ってくる脚が一瞬映る。
脚は、すっとユニットバスへ入っていった。
ああ、E子が自分の分担を終わらせて、手伝いに来てくれたかな?競争は俺の負けか。
と思いながら掃除機をかけ続けたが、一瞬で何ともいえない気持ち悪さがこみ上げる。何か忘れてる。何かに俺は気付いてない。
脳内で誰かが警告している。それは俺自身なのかもしれないし、別の何かか。
手が止まり、掃除機のスイッチを切る。ユニットバスから音は聞こえない。
頭が混乱した。
おかしい。ユニットバスに誰かが入ったのを視界の隅で捉えたが、出て行く気配は無かった。
そして何より、ユニットバスの掃除は先程終わっている。E子なら、ベッドルームを掃除する俺を見ればそれにすぐ気付くはずだ。
もう一度、今見た光景を思い返す。
脚がユニットバスに入って行くタイミングでも、違和感があった。それはあまりにスムーズに中に入っていったのだ。
入り口の段差を、乗り越えたようには見えなかった。
直感的に何が入ってきたのか理解した。見てはいけない。しかし、ただの勘違いということもある。そう思いたかった。
嫌な感じが全身に伝わり、見えない何かが警告している。やめろと。
だが、俺はゆっくりとそこに向かう。何もないと安心したかったのと、好奇心もあった。
そして、
俺はユニットバスを覗きこんだ。
そこには誰もいなかった。
しかしすぐにおかしな光景に気付く。
ユニットバスのカーテンが閉まっている。
一瞬声をあげそうになる。そんなはずはない。さっき俺はここを掃除した。掃除した後でわざわざカーテンを閉めるようなことはしない。
だが、カーテンは閉まっているのだ。
身体が固まった。考える。
しかしどうしても、今俺の目の前の光景に説明がつけられない。
カーテンを開けろ。そうすれば、何もなく俺の勘違いだったことがわかる。
さぁ早く。
手を伸ばす。
また一瞬身体が硬直する。
さっきからブンブンとハエが飛ぶような音が聴こえる。
部屋の中にハエいたっけ?
いや、耳鳴りか。
開けてはいけない。開けなくては。
開けちゃダメだ。今すぐ開けてくれ。
開けるな。今すぐ開けろ
脳内で声がする。
ほんの一分ほどだったのかと思うが、そこで立ち尽くす俺には数十分にも感じられた。
そのとき、階下から俺を呼ぶ声が聞こえてハッとした。
すぐこの場を離れよう。
理由はなんでも良かった。後で誰かに話せばチキン野郎だと言われるかもしれない。
それでもいい。逃げよう。逃げたい。見てはいけない。
見えない何かに動かされそうで、頭が破裂しそうだった。
部屋を駆け足で出る。
後ろに視線を感じたような気がしたが、振り返らずに進む。
階段の前で脚が止まった。
E子は?
すぐに俺は踵を返した。
振り返るとそこは閑散とした廊下だ。大丈夫。E子が掃除している部屋まで行き、E子を連れて来ないと。
向かいの部屋にE子はいたらしい。
突然入ってきて手を引く俺に驚いたE子は、「どうしたの?」とか「真っ青だよ?」という趣旨のことを言っていたようだが、俺は『下で呼んでるから来て!』と一喝してE子の腕を掴み、早足で一緒に階段を駆け下りた。
その後のことは、よく覚えていない。
俺は階段下のロビーのソファで寝ていたらしく、意地悪女将にこっぴどく叱られた。
その日は調度飲み会のある日で、俺は酒の勢いもあり、我慢し切れずこれまでに起こった不可解な出来事を一人の先輩に打ち明けた。
先輩は黙って俺の話を最後まで聞いてくれた。
そして、「落ち着いて聞けよ」と言って話し始めた。
昔、このペンションで働く学生に霊感のある人がいたらしい。
その頃から今と同じ二つの大学が共同で働いていたそうだが、その学生が山を下りるとき、他大生の一人にあることを告げた。
「実は君は、背中に一人憑いている。俺では祓うことはできないが、引き離すことならできる。」
そうして、置いていったのだそうだ。このペンションに。
やはりと思った。背筋が寒くなる。
しかし、次の先輩の言葉に俺は心臓が止まりそうになった。
「お前も一人で全部やらなくちゃいけなくて大変だろうけど、頑張ってくれよ。みやこさん(女将の名前)にも、もっと手伝ってくれるように俺たちから頼んでやるからさ。」
何を言っているんだ?この人は。
また一瞬、嫌な感じがした。
何か勘違いをしている。重要なことに俺は気付いていない。
なんだ?なんだ?
声が震える。
「いや、E子がいるじゃないですか。」
先輩が「は?」と言った。
いやだからS大の一年のE子が…
脳内で声がする。
お前は気付いていない。目を覚ませ。
お前は気付いていない。目を覚ませ。
「だから、今年はS大の一年が少なくて、うちのこもり先には一人も来てないんだって!」
先輩の顔が若干引きつっていた。
いや、だって…
と言って酒を囲むテーブルを見渡す。十人ほどのメンバーが和やかに話しているが、E子はどこにもいない。
え?あれ?ああ、トイレ?あれ?
E子は いな い?
そ んな はずは ない。
E子は一緒に掃除をして、今日だって…
ここに来てからのことを必死に思い出す。思い出そうとしても、E子の記憶は曖昧で手を伸ばしたその先から離れていく。
そういえばおかしなことがあった。飲み会でグラスを準備するのはいつも俺の役割だが、決まって先輩から一つ多いと言われる。ちゃんと数えたはずだったんだが。という記憶が蘇る。
そういえば女将が発見する髪の毛は、いつも長い黒髪だった。男しか泊まらなかった部屋でも、いつも長い黒髪だった。
女将が俺をいびるために自分の髪を抜いてるのかよと思ってたけど、あれはもしかして
「D(俺の名前)、お前大丈夫か?」
と先輩に肩を叩かれ我に返った。
その後、先輩の質問には適当に答え、受け流した。俺は急に眠くなったと言い、飲み会を抜け出して寝室に戻った。
長い夢を見ていたような気がする。
その夢から、俺は覚めたのだ。
もう、E子には会えないだろう。
怖いというより俺は寂しかった。
もう一度会いたかった。会っていろいろ話したかった。
思い返そうとするほどに、E子の記憶は霧のように薄くぼやけていく。
まだ何も話していなかったのかもしれない。まだ何もE子のことを知らなかったのかもしれない。
それすらも、もう思い出すことができない。
そうして、また普段の忙しい日常に戻っていった。
何事もなかったかのように。
ただ一つ変わったことがある。夜中に突然目が覚めるようになったことだ。
週に2、3回そんなことがあった。
金縛りではない。ただ疲れているだけだろうと思っていたが、冬が終わり自分のアパートに戻っても、しばらくそれは続いた。
それがいつまで続いたかは覚えていない。山々が名残り雪のベールを脱ぎ、本格的な夏を迎える頃には俺はサークルを辞め、バンド仲間と大いに遊んでいた。
その頃には、もう突然目が覚めるようなことはなかったように思う。
最近地震の前に目が覚めるようになって、なんの気は無しにある先輩にそのことを話した。『夜中に急に目が覚めることないですか?』って。
すると、その人は雪山で俺が体験したことなど知らないはずなのだが、こんなことを言うのだ。
「夜中に突然目が覚めるのには原因があるのさ。それは誰かが家の玄関に訪ねてきているんだよ。」
俺はもうE子の輪郭すら思い出せない。
E子の記憶はあれからほとんど消えてしまった。まるで雪が溶け、水となって流れ出し、純白の山々が新緑に塗り潰されるように、俺の中でE子の記憶は掻き消されていった。
ただ、白い雪を見ると今も思い出す。E子の透き通るような白い肌と眩しい微笑みを。そして、E子にまたいつかどこかで会えるような気がするのだ。
雪は溶け、春が来る。しかし季節が巡れば、また冬が訪れる。
今はまだ会えないが、いつかきっと